ARTICLEワイン記事和訳
本記事は著者であるジャンシス・ロビンソンMWから承諾を得て、
Jancisrobinson.com 掲載の無料記事を翻訳したものです。
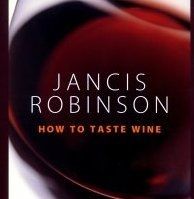
2021年12月2日 最近、新型コロナウィルス感染症の後遺症による嗅覚障害や味覚の変化に多くの人々が苦しんでいるようなので、私がかつて嗅覚の完全な機能不全を経験した際の記事を再掲したいと思う。アリスター・クーパーMWの体験談や、ボルドーのISVVが開発した嗅覚回復法なども参照するとよいだろう。
2008年10月25日 この記事はフィナンシャル・タイムズに掲載された記事のロング・バージョンだ。
私にとって最近の記憶の中で最も甘い香りの記憶は床板の隙間から降りてくるチーズスティックの香りだ。その時私はロンドン北部、イズリントンにある建物の地下にいた。その家の主のマスター・オブ・ワイン論文のためにブラインドでスパークリング・ワインをテイスティングする12名のテイスターの一人だったのだ。発酵したシャルドネとピノ・ノワールの果汁、二酸化炭素、そして死んだ酵母細胞と共にボトルに閉じ込められ、ようやく解き放たれた泡立つワインの香ばしい香りが漂う部屋の片隅で、私の鼻は予期せぬ香りを感じ取った。ワインとは別の種類の発酵。乳酸的でチーズっぽい。でもチーズではない。天井から降りてきたその香りはチーズ味のフレークのようで、私はチーズスティックだろうと予測していた。
テイスティングを終えて自分の採点結果を提出し階上に出ると、未来のMWが我々をねぎらうための液体と固体を手に佇んでいた。その時、私は喜びのあまり彼の胸に飛び込みそうになった。私が地下であの香りを嗅いだ真上にはまさに、チーズスティックの山が乗った皿が置かれていたのだ。まさにこの時、私がプロ人生の中で最も恐怖に駆られていた時間と決別を果たしたのだった。
振り返ってみるとそれは4カ月間で3回目のインフルエンザの症状から始まった。あまりにつらかったので、ワイン審査会のためのケープ・タウンへのフライトを24時間延期したほどだ。なんとか搭乗してお気に入りの「睡眠薬」をすすっていた時、恐ろしいことに気が付いた。ド・グレンデル・シラーズ2004が、まったく何の香りもしなかったのだ。この時が人生で最初の、そして願わくは最後であってほしい、自分の鼻を何かに近づけた時にわずかな香りすら感じられなかった瞬間だった。
私は(下に紹介した)著書のタイトルでもあるテイスティングの手法について何度も講演をしてきた。その中でも私の十八番は、風邪や鼻づまりなどで食欲を失うのは嗅覚がなくなることで食べ物の味がないように感じられることを引き合いに出し、味わいを感じるために嗅覚がどれほど大切であるかを伝えることだった。
そのわずか3週間前、コークの近くにあるバリマルー・ハウスで私はワイン愛好家向けに味覚にまつわる講演をするため、1日を過ごした。エクササイズでは鼻をつまみ、目隠しをした状態ですりおろした人参とリンゴの区別ができるかどうかを試した。バリマルーでは自家栽培もおこなっており、リンゴは非常にリンゴらしく、人参も人参のエッセンスを体現したものだったにもかかわらず、決して全員が正解できたわけではない。そうなのだ、私がこれまで30年以上繰り返しているように、香りというのは味覚にとって欠かせない要素なのだ。
生理学者ならよく知っているように、風味に関わる感覚器は全て鼻の上部に集中している。この上なく敏感で遺伝学的にプログラムされた、その人固有のコンピューターと言えるもので、1万種類もの香りを嗅ぎ分けることができるとされている。口蓋の後ろ側にはこの嗅覚分析装置へ通ずる道があるため、意識的に何かの匂いを嗅ぐ習慣のない人でも、なんとなく物の味やにおいがわかるようにできている。だが我々のようなワインのプロは最大限の情報をそこから得ようとする。だからこそ、我々はワインを口に入れる前にその香りを慎重に嗅ぐのだ。それは尊大で馬鹿々々しいしぐさに見えるかもしれないが、ワインを口に入れることで起こり得る酔いなどの感覚に身を任せる前に、何よりも重要な香りとして、ワインが発してくれているメッセージをすべて吸収しようと試みているのだ。嗅覚が非常に大事であり、それが大きな喜びももたらしてくれるものであるからこそ(そして欠陥臭は警告も与えてくれる)、ワインと同じように食品の匂いを嗅ぐということにも意味があると言えるだろう。
私自身、20代でワインを学ぶまで誰にも教えてもらえなかったから、この嗅覚というものがいかに活用されていないかということもよく知っている。だから母親として、自分のこともたちには、彼らが言葉を理解するようになるやいなや、鼻を使うことを意識的に勧めてきた。おかげで息子は私のシャンプーの香りを嗅いで、18か月前に宿泊したホテルのものだと言い当てるし、娘は非常に強い嗅覚を生かし、暇さえあれば冷蔵庫の見張り番として働いてくれている。おそらく3人の子供たちは有毒ガスや汚染された食品の被害にあうことはないだろう。ところが昨年、毎週何百種にも及ぶワインの香りやニュアンスを嗅ぎ取ることを生業としていた私が、完全にその機能を失い、嗅覚の完全な不全に陥ってしまったのである。
それは本当に恐ろしい体験だった。かつてひどい鼻づまりを起こした際には、そこにあるものの香りがほんのわずかにしか感じられないという経験をしたことはあったが、今回は本当に何も感じないのだ。私は何度も自分の手を鼻に近づけ、皮膚の匂いを感じ取れるか試してみたが、無駄だった。南アフリカ航空の香り付きの石鹸でも同じことだった。パールでは、審査員たちが宿泊予定のホテルへ到着するところから、ほろ苦い経験をすることとなる。前回の滞在時にはわら葺き屋根から降りてくる干し草とルイボス茶が混ざり合ったような、何とも言えない、いかにも南アフリカという香りに強く出迎えられた。ところが今回はそれの香りすら、いや、とにかく何も感じなかったのだ。かつてそれがどんなものだろうと想像していた、無嗅覚という現象に直面する恐怖をついに味わうことになったのだ。無嗅覚は人口の数パーセントに見られる症状で、通常は器質的な欠陥か、事故によるものだ。
その朝、ワインのテイスティングに向かうため庭を歩いていくのは苦痛以外の何物でもなかった。私は花の茂みを見つけるごとに、何らかの香りを感じられるのではないかという淡い期待をもって鼻を近づけた。だが何も感じなかった。それはこれまでに感じたことのないほどの当惑だった。小さなグループで一連のワインのテイスティングを行うのは本質にかかわる作業だ。自分の印象と点数を仲間と突き合わせ、意見の一致するスコアを探るからだ。自分の状態を隠すことは愚かなことだし、絶望しか生み出さない。南アフリカで最も著名なワイン・ライターであり、このワイン審査会の主催者でもあるマイケル・フリジョン(Michael Fridjhon)は非常に同情的で、私はもしかしたらこういうことは珍しくないのかもしれないと感じた。彼は点鼻薬や鼻炎の薬などもくれたが、まったく効果はなかった。だからワインについて議論する際、私はパネル・チェアだったにもかかわらず、同席した審査員たちにそれがどんな香りなのか尋ねなくてはならないという哀れな状況だった。
だがそれでも、口内で感じることだけを基準に採点している私と、香りという間違いのない恩恵を享受している同席のジャッジたちの間には明確な一致が見られた。口の中では香りのようなニュアンスを感じ取ることができないかもしれないが、口の中の食品や飲み物の渋みのような感触を感じられるだけではなく、甘み、酸、苦み、塩味、そして強さなど、私が「ワインの三次元的感覚」と呼ぶものを感じられるのだ。
渋みは若いワインによく感じられるもので、頬の内側が乾くような感覚だ。赤ワインの中でも口の中から唾液がなくなるような感覚をもたらすものはタンニンが強い(タニックtannic)と言われる傾向にある。ちなみに白ワインにも同じような感覚を覚えることがあり、果皮に由来するフェノリックによるものだが、タンニンという言葉を使うことはない。テイスティングは非常に個人的で主観的な作業なので、それに使われる言語と手法は厳密さに欠ける場合がある。例えば、つい最近まで我々は、舌は4つの味覚をそれぞれ違う場所で最も敏感に感じるため、それをワインの三次元的な把握に使うことを規範としてきた。すなわち、舌の先端では甘み、後方では酸、塩味は(灌漑用水に含まれることも多いのでワインでも一般に使う表現となってきたが)舌の前側面、苦みは舌の端からもっとも遠い平らな部分が敏感だとされてきたのだ。しかし現在では、その分布は不正確であるとされており、さらに5つ目の味覚、私自身は日本酒の記事でよく使う、「ウマミ」も考慮するようにしなくてはならない。
だが、主に感謝しよう、今私は再び香りを感じている。酸が高いと思われるワインを嗅ぐと、舌の側面がチリチリとする感覚に見舞われる。次に来る酸という刺激に唾液の分泌の準備が始まったということだ。そしてアルコール度数が非常に高いワインを飲んだり、吐き出したりすると口の後方に温かく焼けるような感覚がある。確かなことは、そして南アフリカのワインの審査を口だけで行ってもなお比較的正確さを保つことができた理由を説明できるかもしれないことは、口の感覚だけでもワインの品質の目安となる2つの重要な「次元」を探ることができるということだ。つまり甘さと酸など、全体として調和が取れているのか、またワインの余韻が飲み込んだり吐き出したりしたあとどのぐらい長く感じられるかという2点だ。
プロのテイスターはもちろん、公の場でワインを吐き出すことに何の躊躇もない。場合によっては1日に100種ものワインをテイスティングしなくてはならないのだから当然だ。逆に飲み込むことは賢明ではない。ただ、私の経験上、この吐き出すという行為が社会的な意味でワインを飲むという喜びを損なうことはない。ワインのテイスティングとワインを飲むことは全く異なる性質を持つからだ。そもそも、多くの人がワインと関連付けて考えるリラックスという言葉はテイスティングには全くあてはまらない。むしろ、極限までの集中力が求められるのがテイスティングであり、私の場合は年齢を重ねるとともに獲得してきたものだ。これは医学書などで懸念されている加齢に伴う知覚の衰えを補ってくれているのかもしれない。テイスティングはまた、訓練も必要とする。私は若いころ、ワインのテイスティングは社交的な催しの一環として捉えていた。だが今の私のテイスティングはこの上なく退屈だ。私は他のものには目もくれず、グラスの中のワインについて雑然としたノートに書き留めるか、ベタつくキーボードで打ち込むかしかしない。歯はひどい状態になる。特に若い赤ワインの場合は色素によって黒ずむし、酸はエナメル質を侵食する。
よく質問されるのは、プロはワインのテイスティング前にどんな準備をするのかという点だ。正直、その答えはほとんどない。気圧が高い方が味わいを正確に、鮮やかに感じられる点では助けになるだろう。ミント味の歯磨き粉は味覚を殺してしまい、直後に口に入れるワイン(あるいはジュースでも)を不味い金属的な味わいに変えてしまう。強い香辛料には味覚が乗っ取られる(ただ嗅覚は大丈夫だ)。ただ、一般の多くの人が考えるようにワインをワインの間に必ず水で口を漱ぐ必要はない。ワインが適切な順番で(強いものや甘いものを最後に)テイスティングする限り、ワインを連続して、そして同じグラスからテイスティングすることに問題はない。前のワインが残っていることよりも洗浄液が残っていた場合の方が大きな混乱の原因だ。
もう一つ、数十年間のテイスティングに際し頻繁に訊かれるのはスーパーテイスターというものが存在するのかどうかという点だ。いわゆる生まれながらにして人よりも優れたテイスターはいるのだろうか?私は嗅覚を失う前、この考えにはどちらかというと否定的だった。当時の私はきっぱりと「ごく一部の無嗅覚症の人を除いて、十分に興味を持てば良いワイン・テイスターになれる」と答えていたものだ。これは自分の経験も含めてであり、マスター・オブ・ワインのテイスティング試験を受けた時、私は妊娠中だったという点も付け加えておきたい。しかし、嗅覚を失ってしばらく生活をし、自分の嗅覚を再評価してみると、ありがたいことに、それがかなり鋭いという点に気づいた(チーズスティックに感謝だ)。私は子供のころから、自分の経験や場所と密接に関連した匂いの記憶を持ち合わせていた。例えば刈りたての芝や太陽の下で温まったトマトなどだけではなく、ブライスバーグ教会の匂い、祖母の家の地下室、石灰主体の肥料から特定の種類のテニスボールなどまで、様々だ。
そして2006年の夏、私はマスター・オブ・ワイン協会がナパ・ヴァレーで開催したシンポジウムに参加した。その際仲間のMWの一人が我々全員を対象に、無意識のうちに味蕾の数の多さを知ることができるという、ちょっとしたテストを行った。その結果、一般的なレベル、あるいはハイポ(抑制)テイスターと比べてハイパー・テイスターであったのは私も含め女性が圧倒的に多かった。もちろん、単に普通のテイスターであるという結果よりはワイン・ライターとしてありがたい結果だとは思うが、このことで何か私が変わるわけではない。テイスティングはただ一貫して、自分の経験、感覚、好みに忠実であるべきというだけだ。
誤解のないように書いておきたいのだが、我々はだれもが多くの味蕾を持っている。人間の鼻は化合物によっては1万分の1程度の濃度でも検出が可能だが、味覚に関しては人によって敏感な風味が大きく異なる。さらに話が複雑なのは、客観的なテイスティング・ノートを書こうとする際、一般的かつ客観的で検証可能な言語が存在しないという点だ。テイスティングは非常に個人的な経験であり、たとえ誰かが「スパイシー」と表現しようとする香りでも、それを抽出して他のテイスターが感じているものと比較することはできない。それでも結果として、テイスティング・ノートがなんとなく理解できるというのは不思議なことだと言える。
南アフリカから戻ったとき、私は自分のワインを表現する能力は永遠に失われたのだと感じていた。ワイン愛好家で、子供たちの扁桃腺でお世話になっている耳鼻咽喉科の専門医でもある友人にすがる思いで連絡すると、ありがたいことに彼はアルプスでの休暇を返上し、同僚に私を紹介してくれた。それから2,3週間の間、私は強力な点鼻薬や飲み薬を試したり、子供たちが私の鼻先に強烈な匂いの軟膏を塗ったりしたものの、匂いのない世界に変化はなかった。ごまかしが大嫌いな私は世界中に自分のキャリアの終焉を告げ、全てをジュリアに託そうとまで考えていたのだが、この賢明な専門医はそれを不必要で馬鹿げたアイデアだと一蹴した。おそらく彼は、私はその時とても信じることができなかったのだが、私の愛すべき嗅覚が戻ってくるとわかっていたのだろう。
結局何が起こったのかはわからない。ただ、息子が(現在は見られない旧バージョンの)メンバーズ・フォーラムに2004年に書き込まれていたコメントで「ワイン・テイスターに最適な鍼灸」「鍼灸とテイスティング」などを見つけたことは覚えている。そして優れた鍼灸師の印象は非常に鮮明に覚えている。最初の1時間の施術後、私の鼻は急に活動を始めたのだ。その夜のディナーで、私は熟成したブルゴーニュの赤ワインの余韻に残るキノコの香りをついにかぎ取ることができた。そして、幸いなことにそれからの回復は非常に早かった。
How to Taste
本書の完全改訂版はイギリスでは11月3日に、アメリカでは11月25日に発売されたばかりだ。(訳注:2008年当時の話です)
(原文)

